細かいものを観察する時には,顕微鏡が使われます。電子顕微鏡のような特別な装置は,非常に高い倍率で観察ができますが,普通の光学顕微鏡では,600Xとか1200Xとかが最大倍率になっているようです。それより高い倍率は得られないのでしょうか?
 答えは,それ以上倍率を高くすると,ぼやけた像が大きくなって行く,ということになります。数字の上で倍率を大きくして行くことはできますが,ぼやけた像で観察しても,細かいものが見えたことにはならないので,光学顕微鏡の倍率には限界があるのです。普通の光学顕微鏡で像が見える大きさの限界は,使う光の波長程度であることが分かっています。可視光線は波長が500nm(0.5μm)程度ですから,それより小さいものは,いくら技術が進歩してもちゃんとした像として見えないのです。電子顕微鏡では光の代わりに電子を使いますが,電子は波長が非常に短いので,分子くらいの小さいものでも像が見えます。
答えは,それ以上倍率を高くすると,ぼやけた像が大きくなって行く,ということになります。数字の上で倍率を大きくして行くことはできますが,ぼやけた像で観察しても,細かいものが見えたことにはならないので,光学顕微鏡の倍率には限界があるのです。普通の光学顕微鏡で像が見える大きさの限界は,使う光の波長程度であることが分かっています。可視光線は波長が500nm(0.5μm)程度ですから,それより小さいものは,いくら技術が進歩してもちゃんとした像として見えないのです。電子顕微鏡では光の代わりに電子を使いますが,電子は波長が非常に短いので,分子くらいの小さいものでも像が見えます。でも光を使った計測は,分子に関して様々なことを我々に教えてくれます。例えば「高速の動き・変化を光で見る方法」で解説したように,分子の高速な挙動を知るには,光を用いる観測が不可欠です。光を使って,細かいものをはっきり見ることができれば,いろいろな可能性が出てきそうです。
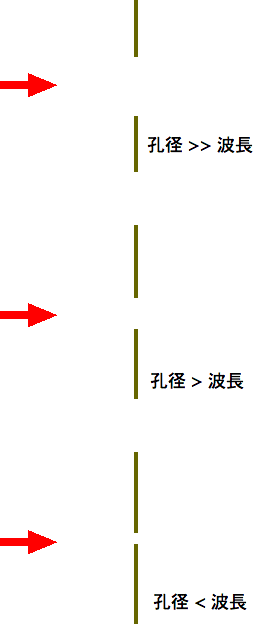
平行光線をレンズで集光すると,焦点の位置では光が「点」になります。でもこの「点」は本当の意味での点ではなく,大きさ(広がり)を持っています。どんな高性能のレンズを使って,注意深い実験をしても,この「点」の大きさは光の波長程度より小さくはできません。これを回折限界といい,前に出てきた顕微鏡の像の限界の元になっています。空間を伝わる光は,これよりも小さく絞ることはできないのです。
話は変わりますが,非常に薄い金属板に小さな孔をあけ,そこに光をあてることを考えます。孔が十分な大きさがあれば,光はその孔を通って,金属板の反対側に出てきます。孔をどんどん小さくして,光の波長よりも小さくしてしまうとどうなるでしょうか? 光は孔を抜けてこられなくなります。これは,上にでてきた回折限界と関係しています。
ところが,その場合でも,孔のごく近くを詳しく調べると,孔の大きさ程度の距離までは,金属板の裏側に光がもれ出すことがわかっています。それよりも遠くには,光は伝わらないのです。孔からごく近くにある物体は,もれ出す光に照らされて,光が来たことを感じることができますが,少しでも孔から離れると,光を感じることはできなくなります。このような小さな孔のごく近くだけに分布する,空間を伝わらない光を,近接場光と呼びます。近接場光は孔の大きさ程度の空間にのみ存在するので,例えば100nm(0.1μm)の孔をあければ,100nmくらいの空間だけを照らすことができます。つまり,回折限界よりも小さい空間を照らすことができる,ということになります。孔のすぐ近くに蛍光色素の分子があれば,その分子は近接場光を吸収して,蛍光を出します。蛍光色素が孔のすぐ近くにないと,蛍光は出ません。
鉄筋の建物の中では,窓の近くでないとラジオが入りにくいのはご存じだと思います。ラジオの電波は,波長が数メートル以上あること以外,基本的な性質は光と同じです。鉄筋の建物の壁は金属板の役割をしており,窓が小さな孔の役割をしていると考えると,上の近接場光の状況と,建物の中のラジオの状況が対応していることがわかります。窓は1〜2mの大きさですから,電波の波長と同じか少し小さいくらいです。窓の近所では電波の近接場があるのでラジオ放送を受信できますが,窓から奥にはいると,電波が伝わってこなくなるのでラジオが入らなくなる訳です。

 実際には金属板にそんなに小さい孔をあけることはできません。そのかわり,円錐状の金属膜の先端に,数十ナノメートルから数百ナノメートルの直径の孔をあけた「近接場プローブ」を用います。この先端に向かってレーザーの光を入射すると,先端のすぐ近くだけに近接場光がしみ出します。実際の近接場プローブは,光ファイバーの先端に,特別な方法で作成し,レーザー光はその光ファイバーの反対側の端面から入射します。
実際には金属板にそんなに小さい孔をあけることはできません。そのかわり,円錐状の金属膜の先端に,数十ナノメートルから数百ナノメートルの直径の孔をあけた「近接場プローブ」を用います。この先端に向かってレーザーの光を入射すると,先端のすぐ近くだけに近接場光がしみ出します。実際の近接場プローブは,光ファイバーの先端に,特別な方法で作成し,レーザー光はその光ファイバーの反対側の端面から入射します。いま蛍光色素で非常に細かい模様を描いた試料があるとします。この試料の表面ぎりぎりのところに,近接場プローブの先端を近付けると,プローブ直下に蛍光色素があれば蛍光が観察され,色素がなければ蛍光は出てきません。そこで,試料の表面に近接場プローブを近付けたまま,出てくる蛍光を観測しながら,試料面を縦横に隈無くなぞって動かします(「走査」といいます)。近接場プローブのそれぞれの位置で,蛍光の強さがどれだけだったかを記録して行くと,蛍光色素の模様が見えてくることになります。
上に述べたように,近接場光は,孔の直径程度の大きさの空間領域にだけしみ出しています。そのためこの方法では,近接場プローブを十分細かく動かしてやれば,孔の直径程度の大きさの細かい形まで,ちゃんと像として得ることができます。つまり,この方法では光を用いていますが,普通の光学顕微鏡よりもずっと小さいものまで,その形を知ることができるのです。また電子顕微鏡などと異なり,光を用いているため,小さなもののスペクトルをとる事ができ,またレーザーパルスを使えば分子の高速の変化をとらえることもできる可能性を持っています。このような原理で微細なものの形や構造を見る方法を,「走査型近接場光学顕微鏡」といいます。
近接場光学顕微鏡では近接場プローブを表面スレスレに近付け,そのままある面積を隈無く,かつ細かくなぞる必要があります。これにもいろいろと工夫が必要です。
 固体の物質の中には,電圧をかけると,その電圧に応じた長さだけ,わずかに伸び縮みを起こすものがあります(圧電効果といいます)。これを利用して,圧電効果を示す固体で機械仕掛けを作れば,物の位置を動かすステージができます。伸び縮みがわずかなので大きく動かすには不向きですが,逆に小さく動かしたい時にはこれを使うのが便利なのです。電圧を調整すれば,好みの場所に,細かく物を移動することができます。
固体の物質の中には,電圧をかけると,その電圧に応じた長さだけ,わずかに伸び縮みを起こすものがあります(圧電効果といいます)。これを利用して,圧電効果を示す固体で機械仕掛けを作れば,物の位置を動かすステージができます。伸び縮みがわずかなので大きく動かすには不向きですが,逆に小さく動かしたい時にはこれを使うのが便利なのです。電圧を調整すれば,好みの場所に,細かく物を移動することができます。あとは,表面スレスレを保つ工夫ができれば,圧電効果を用いて近接場プローブを走査して,試料の像を得ることができます。これにはいくつかの方法がありますが,走査型近接場光学顕微鏡では,「シアフォース(ずりの力という意味)法」という方法がよく用いられます。光ファイバーでできた近接場プローブを,小さく振動させながら試料の表面に近付けて行きます。プローブの先端が表面から遠い時には,自由に振動していますが,表面に接すると,振動できなくなります。表面のごく近く(10nm程度)では,表面に近付くと次第に振動が小さくなり,遠ざかると大きくなります。そこで,振動の幅を計測し,その幅がある一定値になるように,プローブと表面との距離をうまくコントロールすれば,表面スレスレを保つことができます。このようなコントロールは,電気回路を使えば可能で,注意深く調整すれば,試料の表面から10nm前後の距離を保ったまま,近接場プローブを走査することができるのです。